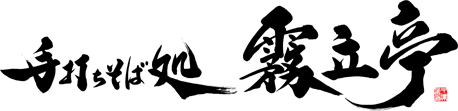ソバノキって、どんな木?
「ソバノキ」という木があります。実際には蕎麦の原料になる“ソバ”とはまったく別の植物で、とある樹木の別名です。

その木の正体は、ブナ。
北海道の渡島半島から九州までの広い範囲に分布するブナ科の落葉広葉樹です。道内では黒松内町がブナ北限の町として知られています。
道北の幌加内町は分布域からさらに北に位置しているためなじみがありませんが、一般的には日本海側の北国に多く、青森県から秋田県にまたがる白神山地のブナ純林は1993年、世界自然遺産に登録されました。
そのブナにどうして“ソバノキ”という、ちょっと紛らわしい別名がついているのでしょうか?
ポイントは形
鍵を握るのは、「実のかたち」。


ブナの実は、三角錐のようなかたちをしていて、表面に角ばった“稜(りょう)”があります。この稜が、蕎麦の実にも見られる特徴であることから、ブナの実は「稜のある実=ソバグリ(蕎麦の栗)」とも呼ばれ、そして「その実をつける木=ソバノキ」と呼ばれるようになったのです。

“稜(りょう)”とは、 物の角、とがった部分のこと。五稜郭は五つの”稜”がある郭(くるわ、かこい)という意味ですし、山の背のとがった部分が続いている線を稜線といいますね。
昔はこの「稜」を「ソバ」とも読んでいたため、木の実の特徴である「ソバ(稜)のある実」というのがそのまま名前になったというわけです。
ブナ豊凶の影響
ブナの仲間は、日本の豊かな森を象徴する存在です。本州中部以北の冷涼な地域を中心に分布していて、東北や北海道南部では広大なブナ林が見られます。標高の高い場所にも多く、冷涼で湿潤な環境を好むのが特徴です。こうしたブナ林は、保水力に優れた“緑のダム”としても知られ、私たちの暮らしの水源を静かに支えてくれています。
そんなブナは、実が安定して実るまでに50年ほどかかると言われています。その実も他の多くの樹木と同じように年によって豊凶があり、なかでもブナは結実の周期が長く、豊作年は5~7年に1回程度の間隔で訪れます。
参考サイト
ブナの基礎知識(黒松内町ブナセンター)
https://bunacent.host.jp/bunadata.html
ブナの実は、森の動物たちにとって貴重なごちそう。特にクマにとっては、冬眠前のエネルギー源として欠かせない存在です。ところが凶作の年になると、山の食糧が不足し、クマが人里に姿を現してしまうということにもなります。
実際、東北地方の各県において、ブナの豊凶と捕殺されるクマの数のデータを照らし合わせて解析したところ、凶作の年には捕獲数が多いというデータがありました。
参考サイト
環境省 - 2.ブナの結実にもとづく出没予測
https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5-4a/cause/p13-15.pdf

北海道ではブナの分布は少ないですが、ブナの仲間であるミズナラが昨年(2024年)秋豊作だったようです。冬眠前のクマの栄養源であるミズナラのドングリが豊作だったこともあり、2025年は子グマの数が増えるのではないかと懸念されています。
参考サイト
【クマお兄さん】ヒグマカメラ 冬から春/春のヒグマ対策|NHK 北海道のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/sapporo/20250410/7000074677.html
上手く人間と野生生物の生息環境のバランスを保って平和に暮らせたら…と切に願います。