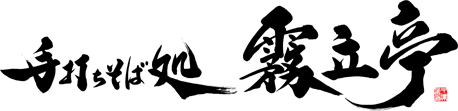そばがき

先日、愛読書『蕎麦の事典』を開いたときにふと目にとまったのは小さな木の葉型のそばがきの写真でした。
『蕎麦の事典』では、そばがきについて次のように記されています。
そばがき【蕎麦掻き】
そば粉を水か湯で練り上げる。そば粉一杯に対し沸騰した湯一杯が常法だが、各自の好みが生かせる。そばがきは原始的なそば粉食の形態であり、ソバの穫れる土地では常食されてきた。五穀を断つ比叡山の回峰行や木食行では唯一の食料でもある。
『蕎麦の事典』(新島 繁):講談社学術文庫|講談社BOOK倶楽部
現在では「そば」といえば麺を思い浮かべますが、日本では縄文時代からすでにそばが食べられていました。当時は実を米のように煮て食べるのが一般的で、その後、石臼の普及によってそば粉を作ることが容易になり、練って餅のように食べる「そばがき」が広まりました。
そばがきの起源は明確ではありませんが、鎌倉時代にはすでに食されていたと考えられています。その後、江戸時代の少し前に「そば切り」が登場すると、そば料理の主流は一気に麺へと移っていきました。
もう一つのそばがき

へぇ~と思いながらページを閉じようとしたとき、隣にもうひとつ「そばがき」という項目があるのに気づきました。よく見ると「そばがき【蕎麦柿】」と書いてあります。
えっ?柿ってあの柿? ダジャレ?
そばがき【蕎麦柿】
1)そば粉に熟柿を肉汁とともに入れて練ったそばがき。
『蕎麦の事典』(新島 繁):講談社学術文庫|講談社BOOK倶楽部
2)串柿を糊のようにし、同量のそば粉を混ぜ、大梅ほどの大きさに丸めたもの。
伊勢貞丈著『安斎漫筆』には、朝出かけるときこれを二、三個食べれば、一日分の食事に当たり飢えることがない、と記してある。
果物の柿を用いた、文字どおりの「そば”柿”」のことでした。
ちなみに、柿を用いたそば料理は、熟した柿をつなぎにした麺の「変わり蕎麦」や、つゆの中に具として柿の果実を入れたものなどもあるようです。
この『蕎麦の事典』にあるそばがき(蕎麦柿)の二つの説明のうち、とりわけ印象に残ったのは(2)の兵糧丸のような形態です。
解説の中で登場する伊勢貞丈(いせ さだたけ)について調べると、次のように紹介されていました。
室町幕府の礼儀,作法を司る伊勢氏の子孫で,江戸幕府に仕えた。有職故実,特に武家故実の研究家として第一人者。
伊勢貞丈(イセサダタケ)とは? 意味や使い方 – コトバンク
武家の制度・典章・調度・器具・服装などにくわしく,精密な考証によって多くの書を著した。
有職故実(ゆうそくこじつ)とは、古来の先例に基づいた、朝廷や公家、武家の行事や法令・制度・風俗・習慣・官職・儀式・装束などのこと。また、それらを研究すること。
有職故実 – Wikipedia
「有識」とは過去の先例に関する知識を指し、「故実」とは公私の行動の是非に関する説得力のある根拠・規範の類を指す。そうした知識に通じた者を有識者(ゆうそくしゃ)と呼んだ。後に転じて「有職」と呼ぶようになった。
なお、文中に「有職」「有識」という表記があるのが気になったのですが、どうやら誤植では無く時を経て変化した表記方法のようです。
本来は「有職」と「故実」とは別の言葉だったのですが、現在では「有職故実」と二つつながった形で使われたり、あるいは本来のようにそれぞれ別の形で使われたりしていますが、意味は三つとも同じようなニュアンスで使われているようです。 「有職」は、本来は「有識」という語で、その通りに「知識が有る」という意味です。それがいつの間にか「有職」という書き方がなされるようになってしまいました。
衣紋道と有職故実 – 有職文化研究所
つまり伊勢貞丈は、幅広い知識を背景に考証を行った「有識者」としての立場の人物であり、その著作『安斎漫筆』は専門家による随筆のようなものといえそうです。
同書には、干し柿を練ったものとそば粉を混ぜて丸めた「蕎麦柿」を、朝に2~3個食べれば一日もつと記されているようです。
ぜひ原文を見てみたかったのですが、原文は草書体で画像化されたものしか見つからず、該当箇所すら発見できず挫折しました;
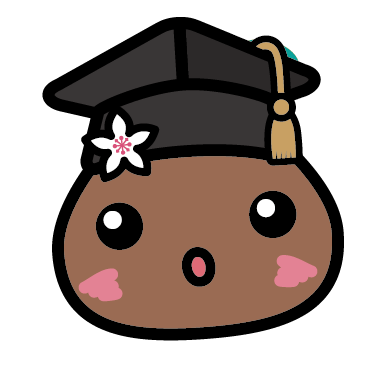
原文のPDFを見ることができます。
安斉漫筆. 巻之1-6 / 伊勢貞丈 考 – 早稲田大学
現代語訳の書籍があったら読みたかったなぁ~。
この兵糧丸タイプの蕎麦柿は、「串柿」つまりは干し柿を「糊のように」ねっとりと練ってペースト状にしたものとそば粉を混ぜて丸めるという作り方です。
きな粉に水飴を練り合わせた「きなこねじり」とちょっと雰囲気が似ているような気もします。(もっとねっとりかも)
最初に引用したように、そばがき(蕎麦掻き)は修行僧の食料でもありました。
そばは穀類の中ではとりわけ植物性タンパク質が豊富で、必須アミノ酸のバランスにも優れています。栄養価の高い保存食としての蕎麦柿は、まさに当時の「エナジーバー」と呼べる存在だったのかもしれません。
ホントにあった!
そんなことを思っていたら、なんと「柿ベースエナジーバー」というものを発見!
干し柿を使った自然派のエナジーバーだそうです。

干し柿を使った「柿ベースエナジーバー」は、山形県庄内地域・地元の農家さんと一緒に収穫した庄内柿、米所庄内が誇る有機発芽玄米、栄養たっぷりのナッツ、オーツなど選び抜かれた食材のみを使用しています。
KAKI ENERGY BAR|柿エナジーバー | SHONAI SPECIAL
山形県庄内の柿に発芽玄米やナッツ、オーツを合わせたものですが、そばは含まれていないようです。
もしそばが含まれていたら、伊勢貞丈が記した「蕎麦柿」の現代版と言えたかもしれませんね!
おまけ)隣の北海道民はよく柿食う客だ
最後に柿つながりの話をひとつ。
北海道では秋になると柿が多く並びますが、実際には道内産の柿はほぼ流通していません。それにもかかわらず、北海道の柿消費量は日本一なのだとか。
背景には、北前船によって山形の庄内柿が北海道へ運ばれていた歴史があります。庄内柿は航路の途中で渋みが抜け、ちょうど食べ頃の状態で届いたことから、北海道の人々に親しまれるようになったそうです。
現在でも庄内柿の約7割(!)が北海道へ出荷されているとのこと。
そして、ここでも登場するのが庄内柿。偶然にも、先ほどの柿エナジーバーとつながりました!
秋の味覚、柿。そばとのつながりは意外と深かったです。