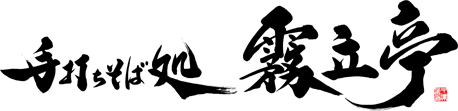栗じゃないよ、そばだよ

ご存じですか?幌加内町のカントリーサインがリニューアルされます。
2025年7月からデザインの公募が始まり、最終候補5案の一般投票が9月に行われ、最優秀賞となった「イトウを抱えるほろみん」のデザインが次のカントリーサインのデザインに決定しました。
某所での告知の際にもちょいちょい「栗」と間違われていましたが…ほろみんは、「そばの実」です。
たしかに栗は秋の味覚の代表格なので、この時期の話題であの形となると栗をイメージしても仕方ないかもしれませんね(笑)
まだまだほろみんの周知が必要なのだと実感したほろグルみ団団長の当店店主(別名”ほろみん伝道師”)。さらにほろみん活動を加速させるとかしないとか(ふふふ
モンブランって何色?
閑話休題。
栗と言えば。
栗のデザートの代表格といえばモンブラン。上のマロンペーストが麺みたいなケーキ。
ところで、モンブランと聞いて何色をイメージしますか?どうやら、世代によってイメージする色が違うらしいです。

子供の頃、モンブランといえば、黄色い卵麺のような栗のクリームの上に栗の甘露煮が乗ったケーキ、というイメージでした。生クリームにイチゴやフルーツがのったものに比べると和菓子風の見た目のせいかちょっと地味な印象で、いただき物の箱を開けて中身がモンブランだった日には、イチゴのやつが良かったなぁ~と内心残念に思っちゃうケーキだった気がします。ザ・昭和の記憶です。
昭和世代にとっては黄色が主流のモンブラン。
ところが、最近はモンブランといえば茶色ですらっと縦長だったり、クリームが細くてほわほわだったり、おしゃれな感じのものが多くなりました。

この茶色のものが本場フランスやイタリアで主流のモンブランなのだそうです。栗を渋皮ごと使ったマロンペーストを使っており、栗の風味がしっかりと味わえることもあり、近年は日本でもこちらが主流といえそうです。
黄色の卵麺風から、見た目はそば風になりました(笑)
昭和世代になじみのある黄色のモンブランは、実は日本オリジナルアレンジ。
お正月にも登場するあの栗きんとんでおなじみ栗の甘露煮で作っているから黄色くなるとのこと。どこか懐かしい優しい味わいなのは、無意識で栗きんとんをイメージしちゃうからかもしれませんね。
栗もそばもグルテンフリー
日本では栗は古くから親しまれてきた食材ですが、「主食」として使われることはあまり多くありません。栗ご飯や栗おこわ、栗がゆなど、お米にプラスして具材として季節を楽しむといった使い方がメインです。
一方、世界、特にイタリアやフランスなどの栗の産地では、小麦の少ない地域で小麦の代用として使われることが多かった食材です。
しかし、栗はそば同様、グルテンフリーの食材。
グルテンフリーの食材をつなぎなしで麺やパンにしようとした場合、頼りになるのはデンプンです。そばは穀類の中でもタンパク質含有量が多く、そのタンパク質がデンプンの糊化をサポートするため、十割でも麺として打つことが可能です(高度な技術は必要ですが)。
一方、栗粉はつなぎなしで麺やパンにすることが基本的には不可能です。栗はそばに比べてタンパク質量が約半分と少ないことも一因ですが、より大きな違いは”頼みの綱”であるデンプンの性質にあります。
デンプンは主に2つの成分から成ります。
| アミロース | 直鎖状で、ゲル化しやすく、硬くなる性質 |
| アミロペクチン | 枝分かれ構造で、粘性が高く、もちもち感を出す |
アミロペクチン、アミロース、前にも聞いたことありますね。ソバゲノムのお話のときでした。
穀物の実に含まれるでんぷんには、粘り気のもとになるアミロペクチンと、粘り気にならないアミロースがある。
十割そばが簡単に? 世界初、もちもちソバを育種 のどごし香りよし:朝日新聞デジタル
コメやコムギなどでは、アミロースの合成にかかわる酵素をつくる遺伝子が機能しなくなることで、アミロペクチンの割合が増え、モチ性が出てくることが知られている。
栗のデンプンについて調べていたら、一つの論文を見つけました。
この論文中では、栗粉のアミロース含有率が 19.6% と報告されています。これは、一般的なうるち米(約17~23%)や小麦(約25%)と同程度かやや低めの値です。
そばと比べてみました。
| 食材 | アミロース | アミロペクチン | 参照 |
|---|---|---|---|
| そば粉(澱粉) | 約27~32% | 約68~73% | *1 |
| 栗粉(澱粉) | 約20% | 残りの約80% | *2 |
*2 栗澱粉の構造と性質(J-STAGE)
この数値を見る限り、栗粉のデンプンはそば粉のデンプンよりも”粘性が高く、もちもち感を出す”とされているアミロペクチンが多いといえます。
アミロペクチンが多いのに、栗粉は水を吸っても粘らない・まとまらないのはなぜか。これは「アミロペクチンの“かたち”」と「粉の状態」が関係しています。
- アミロペクチンの“枝”が短くて、絡みにくい
栗のアミロペクチンは「枝分かれ」が多くても枝が短く、つながりにくい構造をしています。水を吸っても、でんぷん同士がうまくネットワークを作れず、すぐほぐれてしまいます。
例えるなら:小麦粉は“長いゴムひも”が絡み合って伸びるのに対し、栗粉は“短い糸くず”がバラバラに集まった感じ。 - デンプン粒が細かく、表面がかたい
栗のデンプン粒は直径4~6ミクロンとかなり小さいです。しかも表面がかたく、熱で柔らかくなるのに時間がかかる。そのため、水をよく吸っても「全体がまとまる前にバラける」状態になります。
これが「吸水率は高いのに、ぽろぽろ崩れる」理由の一つです。 - たんぱく質が少なく、支える“糊”がない
小麦やそば粉には、でんぷんを支えるタンパク質(グルテンやそばのたんぱく質)があり、粘りを助けます。
栗粉はタンパク質が非常に少ないため、でんぷん同士がくっつく“橋渡し”が起こりません。
結果として、水を加えてもまとまらず、さらさら・ほろほろになります。
イタリアの秋の味覚、カスタニャッチョ

カスタニャッチョは、イタリアのトスカーナ地方の伝統菓子。10月の栗が出回るころになるとマンマがつくる、グルテンフリーのケーキです。
小麦粉などのつなぎになるものも、砂糖も、バターも使わないという潔さ。使うのは水とオリーブオイル、少量の塩とレーズンや松の実や胡桃などのナッツにローズマリーだけ。
起源はローマ時代にさかのぼると言われ、痩せた土地でも育つ栗の粉を使った「貧者のパン」とも呼ばれた存在だったこともあるようです。
カスタニャッチョは、栗のみの甘さに独特の食感があるのが特徴らしく、調べてみると「むにゅっとしている」とか「生地がギュッと詰まって硬くなった餅のような食感」「カヌレのようなむっちりと弾力のある」「エナジーバーのような」といった表現がされていて、おいしくないのかと思いきや、滋味深い味でおいしいという声が多い不思議な焼き菓子のようです。
このカスタニャッチョの食感を分解すると…
| 食感の特徴 | 要因となるデンプンの性質 |
|---|---|
| 冷めると硬くなる | アミロースの老化性(再結晶化)+グルテン不在 |
| むにゅっとした柔らかさ | アミロペクチンの粘性+水分保持+オリーブオイルの潤滑効果 |
栗粉だけをつかいつなぎを使わないことから、栗粉のデンプン構造がカスタニャッチョの独特な食感に深く関わっているんですね。いつか機会があればぜひ試してみたいお菓子です。
でも、食べたことのない現時点の脳内では、なんとなく硬くなったウロコダンゴを焼いたようなものを想像しています…

ほろみんの「栗じゃないよ!」から始まって、遙かイタ~リアまで長い旅に出ていた気がするのに、目が覚めたら深川だった的な妙な夢を見た気分です。(ウロコダンゴは幌加内町のお隣、深川市のお菓子)